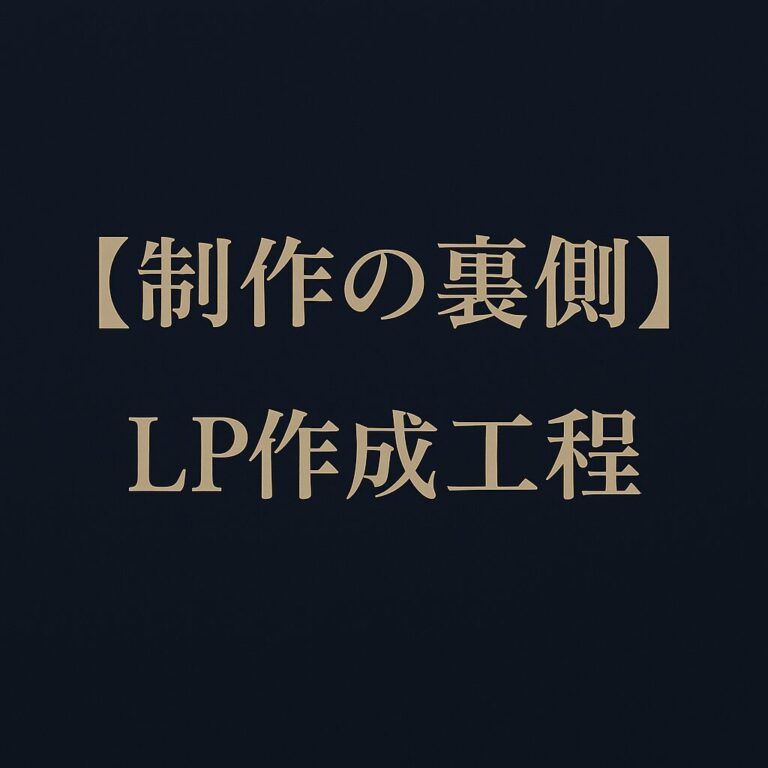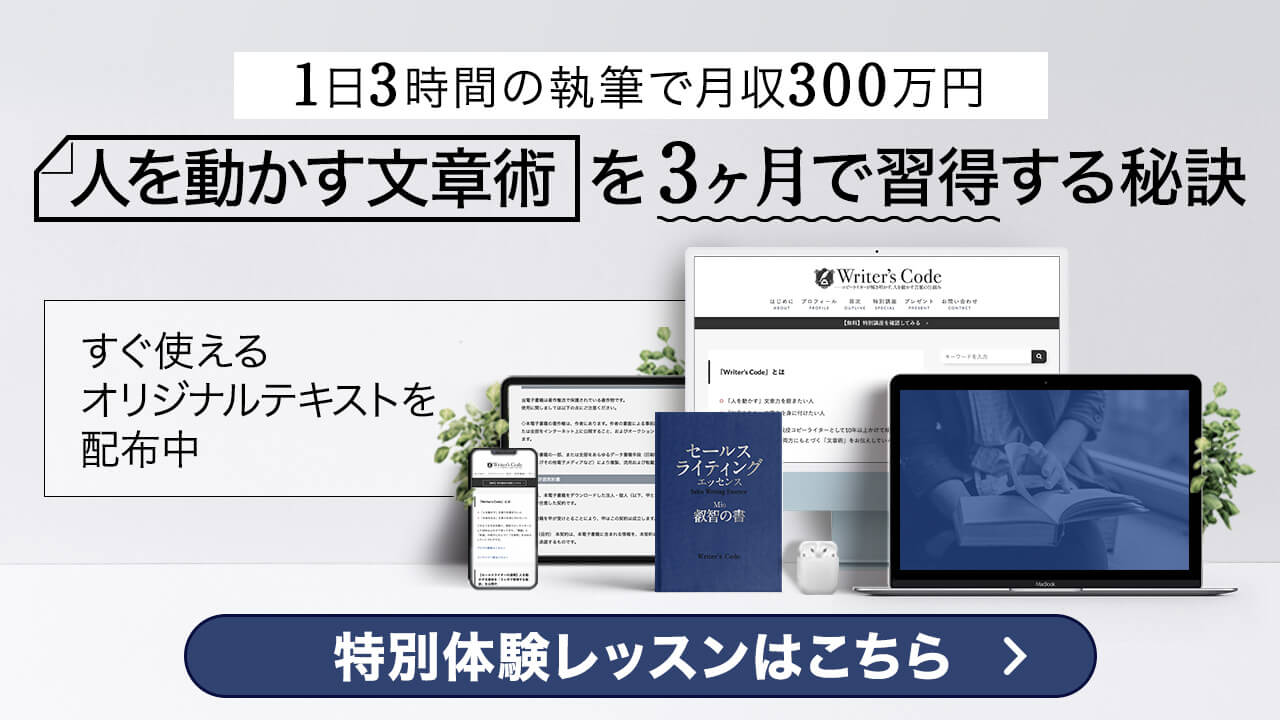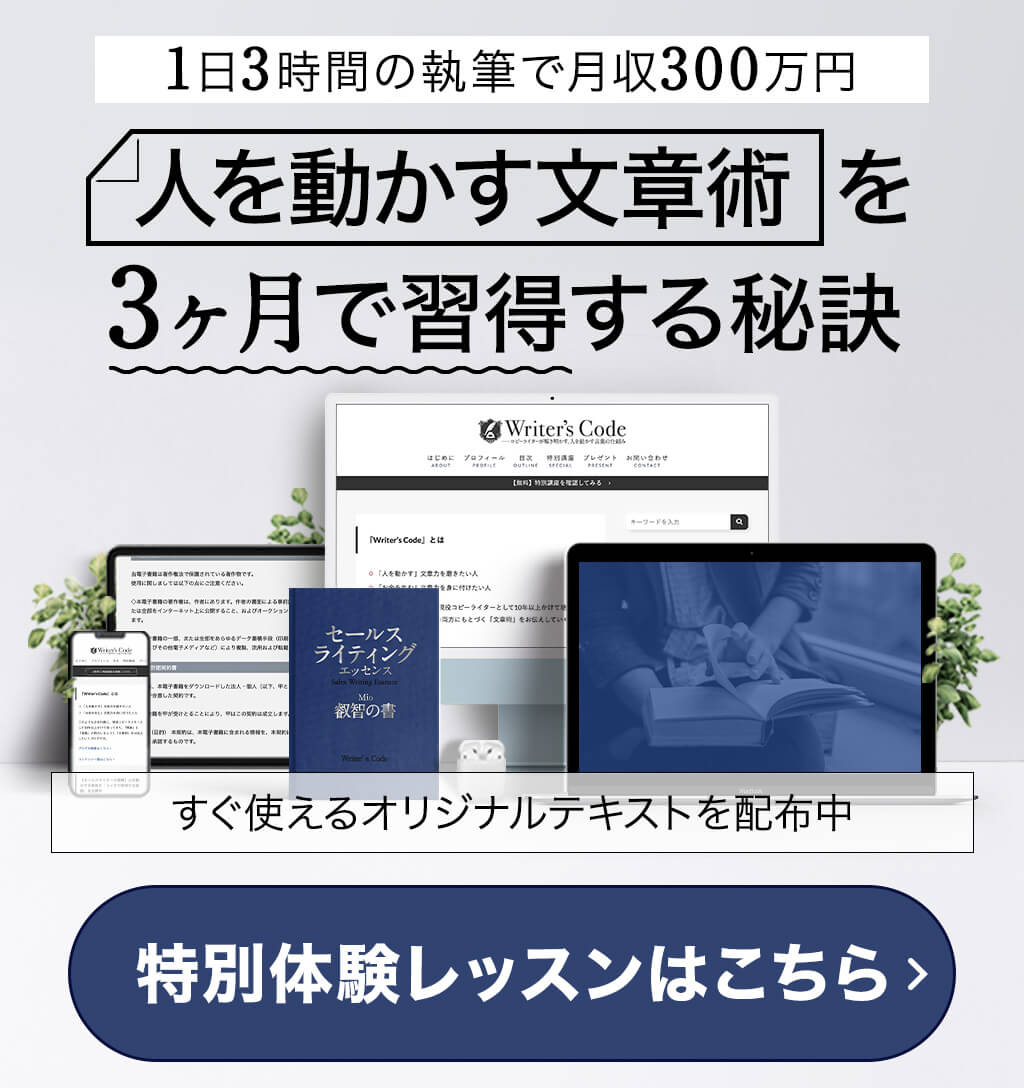松方です。
ふだん私たちがネット上で目にする「ランディングページ(LP)」は、どんなプロセスを経てつくられているのか。そんな疑問を感じたことはないでしょうか。
そこでこの記事では、それらの作成工程や、そのなかでのコピーライターの役割など、「外」からは見えない部分について解説していきます。
LPがネット上に公開されるまでの工程
LPを制作する工程を順番に並べると、以下のようになります。
- リサーチ
- コンセプトメイキング
- 執筆(下書き)
- 執筆(校正)
- デザイン
- コーディング
リサーチ
実際にライティングをする前に必要不可欠なのがリサーチです。
リサーチとは、ライティングするための「素材集め」のようなもの。
商品や見込み客、ライバル商品について調べます。
たとえば、商品やサービスは、どんな人のどんな問題を、どんなプロセスで解決することができるのか。それはなぜか。
などの情報を集め、そのなかでも特に強力な訴求につながる情報を集めていきます。
また「顧客の声」にしても、具体的で強い感情がこもっているものから、漠然と「けっこう良かったです。」というだけの、あまり心に響かないものまであります。
それらの中から、読んだ人の心に刺さる声を「取捨選択」し、また、不足している場合には、みずからヒアリングして集めていきます。
また、競合がどのように販売しているかも重要な情報です。
価格、アピールポイント、具体的なサービス内容。
それらを把握した上で、これから販売しようとする商品が、ライバル商品よりも魅力的に映るようにライティングしていく必要があります。
つまり、リサーチでは、商品やサービスについて、その魅力が最大限に伝わるような素材を集めていくプロセスといえます。
コンセプトメイキング
リサーチで集めた素材をもとに、商品をどのようにアピールしていくかを決めます。
コンセプトという言葉を聞きなれない方もいるかもしれません。
かんたんに言うと、そのページで伝えたい情報をぎゅっと凝縮して『短い言葉』にまとめたもの。
別の言い方をするなら、複数の情報をひとまとめにしたときに、それらを統合する『テーマ』のようなものとお考えください。
たとえば、以下のような特徴を持つ商品を販売するとします。
- YouTubeで再生回数を増やすノウハウを教える
- その方法はスマホ一台で完結できる
- その方法は自分の顔出しをする必要がない
この場合、単に「YouTubeで稼ぐ方法」とするではなく「スマホ一台(手軽)」や「顔出し不要(嫌なことの回避)」という要素も含まれます。
そこで、これらの情報を統合したコンセプトの例としては「顔出し不要のスマホYouTuber養成プログラム」のようにすることが可能です。
その際、読んだ人がより魅力的に感じられるような、つまり、より商品を買いたくなるようなコンセプトにすることがコピーライターに求められます。
執筆(下書き)
コンセプトまで決めることができたら、実際に書いていきます。
ただし、最初から完璧なライティングをしようとする必要はありません。なぜなら、文章の場合、あとから推敲をかさね、ブラッシュアップしていくことができるからです。
また、最初から完璧な言い回しや、正しい表現にこだわり、修正を繰り返しながら書くと、ライティングの際にリズムや勢いが生まれません。書き終えた後で読み返してみると、なんとも読みにくい文章になってしまうことがあります。
なので、まずは完璧さにこだわることなく、リズムや勢いに乗り、どんどん書き出していくことが大切になります。
さらにいうと、キーボードのタイプミスなどで、気が散ってしまう場合には、音声入力を使うのも非常に有効な方法です。そうすれば、完全に、自分が伝えたいメッセージだけに集中することができるからです。
執筆(校正)
下書きをしたら、校正に入ります。具体的には、誤字脱字をなおしたり、より読みやすい表現に修正したり、文章の流れや構成を整えていきます。
人は文書を『書く』ときと、『校正』をするときでは、使う脳の部位が違うと言われています。書くときはクリエイティブな脳の使い方をし、校正のときは慎重かつ批判的な脳の使い方をします。
つまり、脳の性質からしても、執筆と校正を『意識的に区別する』ことは理にかなっているのです。
また、校正で大事なのは、自分目線ではなく、読み手目線で、
- どう感じるか
- どう考えるか
- どんな疑問を持つか
などを客観的に見ていくことです。
とはいえ、読み手目線と言われてもピンとこないかもしれません。
身近なところでいうと、大切な友人や恋人、家族に手紙を書くとして、その人たちがその手紙を読んでどんな気持ちになるかを想像しながら書くようなものです。
きっと、「このように伝えたら喜んでもらえそうだな」とか「この言葉の方がもっと心に届くだろうな」とか思いながら書くと思います。
コピーライティングをする場合には、それが特定の誰か1人ではなく、そのランディングページやセールスレターで狙うターゲット全体の視点を意識しながら書きます。
ここで大事なのは、読み手の心理を考えるときに「当てずっぽう」にならないようにすることです。そのためには、
- 人間の普遍的な心理
- ターゲット特有の心理(悩みや願望など)
これらをよく学び、把握しておくことです。
最初のうちは難しく感じるかもしれませんが、ターゲットの声をよく聞き、リアルに想像できるようになるほど、より正確にターゲット目線で自分が書いた文章を読めるようになります。
また、必ずしも校正は自分一人でやる必要はありません。誰か信頼できるコピーライターやマーケター、またはターゲットに該当する人に読んでもらい、フィードバックをもらうことも有効です。
第三者の意見を聞くことで、自分一人では気づけなかった見落としやアイデアをもらえることも多々あるからです。
デザイン
デザイン依頼
原稿が完成したら、デザイナーにページデザインを依頼していきます。
注意点として、原稿をそのまま渡しても、まず良いデザインにはなりません。
そもそもこちらがどんなデザインに仕上げたいのか、どんなデザインが良いデザインだと考えているのか、その辺りのイメージのすり合わせをする必要があります。
デザインのイメージ事例を共有したり、特にこだわりのあるポイントでは、「フォント」や「文字色」など細かく依頼をしていくこともあります。
これは私のいち意見ですが、ページのデザインは、デザイナーとコピーライターの共作によって完成します。
コピーそれ自体は、ダイヤの原石のようなもの。どんなに魅力的な言葉も、読み手に届かなければ意味がありません。
デザインとは、そんなダイヤの原石であるコピーを磨き上げ、輝かせるもの。
より読みやすく、よりわかりやすく、より心に刺さるように。
コピーが読み手にしっかり届くかどうかは、デザインにかかっています。
デザイン修正
デザイナーが作成したデザインに対して、修正指示をだしていきます。
マーケティングに精通したプロのデザイナーであれば、こちらの意図を汲み取り、「反応の取れる」デザインを仕上げてくれます。
しかし、プロのデザイナーであっても、マーケティングで有効なデザインに詳しくない場合、初稿で良いデザインが上がってくるとは限りません。
その場合、ページの完成度を高めるために、
- 読みやすいか
- トンマナがあっているか
- メッセージが伝わるか
- ぱっと見での違和感はないか
などの修正を繰り返していきます。
ここでの修正依頼も、漠然と「こうしてほしい」と伝えるのではなく、可能なかぎり具体的な事例を共有しながら、イメージのすり合わせをしていくことがコツです。なるべく手戻しがないように、明快な依頼を出していくことが求められます。
コーディング
ふだん私たちが見ているウェブサイトはプログラミング言語によって作られています。そして、そのプログラミング言語を書くことをコーディングと言います。
デザイナーがつくるデザインは、あくまでも画像データなので、それをプログラミング言語を用いて、ウェブサイトとして構築していく必要があります。
ここでの注意点は、パソコンとスマートフォンの両方から綺麗に見えるか、ページの表示スピードは早いか、などをチェックすることです。
コーディングが完了すれば、あとはそのデータをネット上に公開するだけ。
ここまでの流れで1枚のページが出来上がります。
作成期間は1日〜3週間ほど
ランディングページを形にするまでの工程を6ステップで解説してきました。
- リサーチ
- コンセプトメイキング
- 執筆(下書き)
- 執筆(校正)
- デザイン
- コーディング
これらのプロセスは、早いときで1日、遅くて2〜3週間くらいで行います。作成にかかる期間は、どれくらい執筆する分野に関する知識を持っているかや、どれくらいデザインにこだわるのかによって変わります。
すでに経験のあるジャンルや、何度もリピートしてくれているクライアントから受ける仕事であれば、前提となる知識を持っているので、作成にかかる時間も短くなります。
一方で、初めて書くジャンルや、初めてのクライアントの場合には、1からのリサーチが必要となるため、そのぶんだけ時間もかかります。
また、意外と見落とせないのがデザインにかかる時間です。力を入れてしっかりデザインをする場合、ページ1枚あたり3日から1週間くらいかかることもざらにあります。一方で、簡易的なデザインで良ければ、ほんの数時間程度で作ることも可能です。
また、興味深いことに、デザインは、力を入れるほど売れるというものではありません。拍子抜けするほどシンプルなデザインの方がコテコテのデザインよりも高い反応を取れるケースもあります。もちろん、力を入れたデザインの方が売れることもあります。
ただし、プロのデザイナーによる質の高いデザインは、商品やサービスの「世界観」をしっかり伝え、コピーを引き立て、読み手の心を動かすために大きな貢献をしてくれます。
ここぞというときには、商品やサービスの世界観に合わせてしっかりデザインをすることがおすすめです。
一方、スピード重視で進めたい場合には、デザインはシンプルなもので問題ありません。白背景に黒文字、ほとんど画像を使わないようなデザインでも、文章(コピー)が読みやすく、内容が良ければしっかり売れます。
最後に
今日の話はいかがだったでしょうか。1枚のページが世に出るまでに、裏側でどんなことが行われているのかのイメージがこれまでよりもクリアになったなら幸いです。
今回解説したプロセスのなかでも、特に重要な役割を担うのがコピーライターであることはいうまでもありません。どんな訴求を、どんな表現で伝えるのか。ここ次第で結果は天と地ほども変わってきます。
もちろんデザインも大事ですが、デザインが秀逸でも、メッセージが弱いと良い反応は生まれません。逆にデザインが平凡でも、メッセージが優れていれば大きな反応を見込めます。
それだけに私たちコピーライターは、ライティング力を日頃から研ぎ澄ませていきたいものです。
今回の記事が役に立ったと感じていただけなたら、また次回以降もお付き合いください。それでは。